
史上まれに見る3票、2票、2票という僅差の激闘を制し、マヂカルラブリーが優勝を掴み取った『M-1グランプリ2020』。
ファイナルステージだけではない。決勝1本目の1位おいでやすこがと、最下位東京ホテイソンの点差はわずか41点。審査員7人の同大会では最小得点差というのは、10組の実力がより拮抗していたことの証拠だろう。
今回は、実力伯仲だった今大会を振り返りたい。
和牛不在がもたらした意味
出場者がマスクを取るところを集めたあのアツすぎるオープニングVTRの意味や、もっといえばドラマの数々があった敗者復活戦から語りたいことは山程あるのだが、まず大きな山として一つ言えるのは、和牛不在が今大会にもたらした意味だ。
思わずあっと声を上げてしまうような、畏怖の念ほど抱いてしまうほどの構成力の妙。4分にかけて入念に積み上げられていく笑いの厚み。「これは和牛の漫才だ」と分かっていても、毎回その期待を容易に超えていく圧倒的なクオリティに、熱心なファンでなくても毎年のように驚嘆していたと思う。
ここ数年、間違いなく『M-1』は和牛を中心に回っていた。システムやセンスボケ、ツッコミのワードセンスといったものはありつつも、和牛がそこにいるからこそ、伏線の貼り方や最後に向かって盛り上がっていく「構成力」に期待してしまう。
そして、そのトレンドが最高潮にまで高まったのが昨年、ミルクボーイの優勝で終わった2019年大会で結実したように思われる。
そのピークを迎えた翌年の今大会に和牛の姿はいなかった。大会途中で敗れ去ったのではない。エントリー自体していなかったのだ。その不在が、これまでネタの展開や構成力に向けられた視点を、別のなにかに向けさせたのではないだろうか。
代わりにせり上がってきた“文脈”を楽しむ視点
それでは、ネタの展開や構成力の代わりに、どういう要素が浮上してきたのか。それは、お笑い芸人一人ひとりの「生き様」といえるのではないか。言い換えるならばそれは、個々のお笑い芸人の因縁、あるいは“文脈”というべきものだ。
例えば、優勝したマヂラブは2017年に続いて決勝は2度目。前回も今回同様、ボケの野田クリスタルが、ツッコミの村上と没交渉ぎみにひたすらボケまくるネタだった。
これが審査員の上沼恵美子の口に合わず、怒られたことは周知の事実だ。今回は「かつてM-1で上沼に怒られたかわいそうな人達」という文脈が共有されていたからこそ、決勝1本目のネタ「高級フレンチ」を披露する際、せり上がってきた野田が土下座していたことや、「どうしても笑わせたい人がいる」という掴みで会場は爆笑に包まれた。
では、怒られたという2017年の「ミュージカル」のネタはいったいどうだったのか。「ミュージカル」より、今回の「高級フレンチ」がはるかに面白かったのか。そんなバカバカしい問いもない。なぜなら「ミュージカル」が面白いという人は「高級フレンチ」も面白いだろうし、「ミュージカル」がつまらないという人は「高級フレンチ」もつまらないだろう。
つまり、マヂカルラブリーは何も変わっていない。変わったのは彼らの“文脈”を共有したオーディエンスの側だった。
「高級フレンチ」(ネタを知っているとこのタイトル自体が笑えるのだが、実は昨年2019年大会の敗者復活戦ですでに披露されている)は、構成的には不安になるほどオチ前で失速してしまうのだが、それでも無理やり最後までやりきってしまう。
和牛は“文脈”を必要としなかった
ここであえて比べることを許してもらえるならば、和牛は不思議なほど“文脈”を必要としなかった。
毎回優勝をあと一歩のところで逃すという悲劇性を帯びているはずなのに、いざ彼らのネタが始まると、観客を世界に完全に引き込んでしまい、「ネタそのもの」以外に目を向けさせようとしない。
彼ら2人の理知的でスマート、泥臭さと無縁の佇まいも相まって(ただ、本人たちは「苦労知らず」という世間のイメージに軽く不満を持っていることはかつてラジオで語っていたのだが)、来歴不明な不気味ささえただよっていた。

それぞれが回収できた、回収できなかった“文脈”たち
ここ3年ほど、初出場組が目新しさと勢いを味方につけて、和牛を始めとする常連組から優勝をもぎとっていった印象だが、今回に関してだけ言えば、決勝を戦った10組の雌雄を分けたのはこうした“文脈”の強度の差だったように思われる。
ニューヨークは、昨年の大会で松本人志から言われた「楽しそうにツッコむ」問題を決着させるという“文脈”を背負って帰ってきた。さらに、「トップバッターで、しかも歌ネタ」という不本意な形で挑むことになってしまった昨年に対して、今年は3番手というまずまずな順番から、「これぞニューヨーク」というブラックなネタをぶつけられた。
また、ピン芸人で作ったコンビとして決勝初進出となったおいでやす小田、こがけんからなるおいでやすこがは、つい数週間前に突然のレギュレーション改定で「R-1」という「故郷」から締め出された悲劇性を帯びていた。
ぼくが一番印象的だったのは、敗者復活から返り咲いたインディアンスの“文脈”だ。昨年初出場で8番手という絶好の順番ながら、ボケの田渕章裕がネタを飛ばしてしまうなどもあり、下位に沈んだこのコンビ。その後悔をずっと引きずったこの1年だったと推察されるが、敗者復活、決勝を含めて、彼らが一番楽しそう漫才をしていた。これまで個人的には、田淵のボケが先走りすぎており、ツッコミのきむと噛み合っていないという印象だったのだが、この日、特に敗者復活戦のネタはがっちり噛み合っていた印象だった。
一方、決勝で苦戦した様子だったのは東京ホテイソン。ボケのショーゴの考えオチのようなボケに対し、貯めに貯めたタケルが大見得を切るように激しくツッコミを爆発させるスタイルの2人なのだが、決勝にたどりつくまでに少し熟成しすぎてしまった。
数年前までの「親ポムポムプリンだろ!」とバカバカしくツッコんでいたころに決勝に行けていたならば…もしくは、今回も1本目で「親ポムポムプリンだろ!」系を、2本目で今回のネタをしていたら…とタラレバが止まらない結果になってしまった。
ぼくが最も応援していたウエストランドにもいくつもの“文脈”があったが、それが広く共有されていなかったことが致命的だった。例えば、“いぐちんランド”事件がもっと世間的に大問題になっていたら、準決勝までと同様にネタに組み込めていただろう。ただ、それができないほどの絶妙に微妙な知名度だったのが痛かった。
一点、松ちゃんがある程度評価していた(と言っても点数は上から6番目だったが)のがうれしい誤算。よくよく考えてみれば『チキンライス』を作詞した人に「お笑いは今まで何もいいことのなかった奴の復讐劇なんだよ!」のキラーフレーズが響かないわけないか!
一つの“文脈”が終わり、また新たな“文脈”が始まる
素敵だと感じたのは、今大会で優勝候補の一角に挙げられながら8位に沈んだアキナだ。本来は相当ショックだったはずなのに、敗退決定直後から、優勝候補に挙げられながら微妙な結果だったということをすかさずネタにする「恥ずかしい漫談」を次々と繰り出していた。
毎回、勝者の歓喜する姿以上に、敗者たちの佇まいで「お笑い芸人って素敵だな」と思わせてくれるこの大会。
悲しみを笑いに変えながら、また走り出す。M-1が終わり、回収すべき“文脈”が今始まったばかりだ。

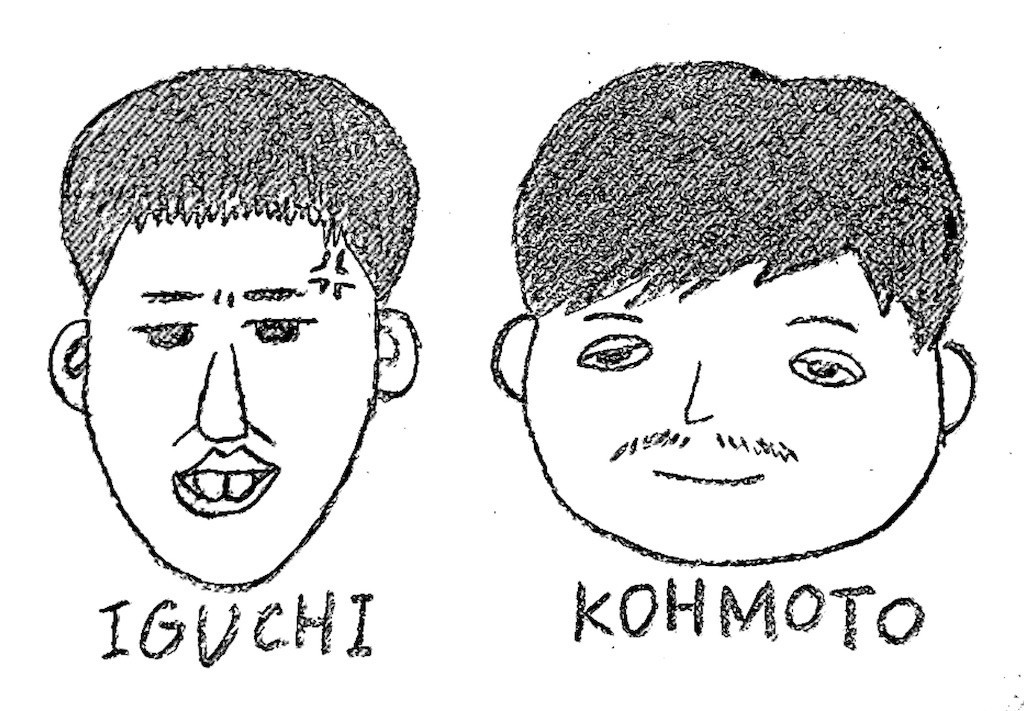


![好きにならずにいられない [DVD] 好きにならずにいられない [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51oXKD7KiQL.jpg)


